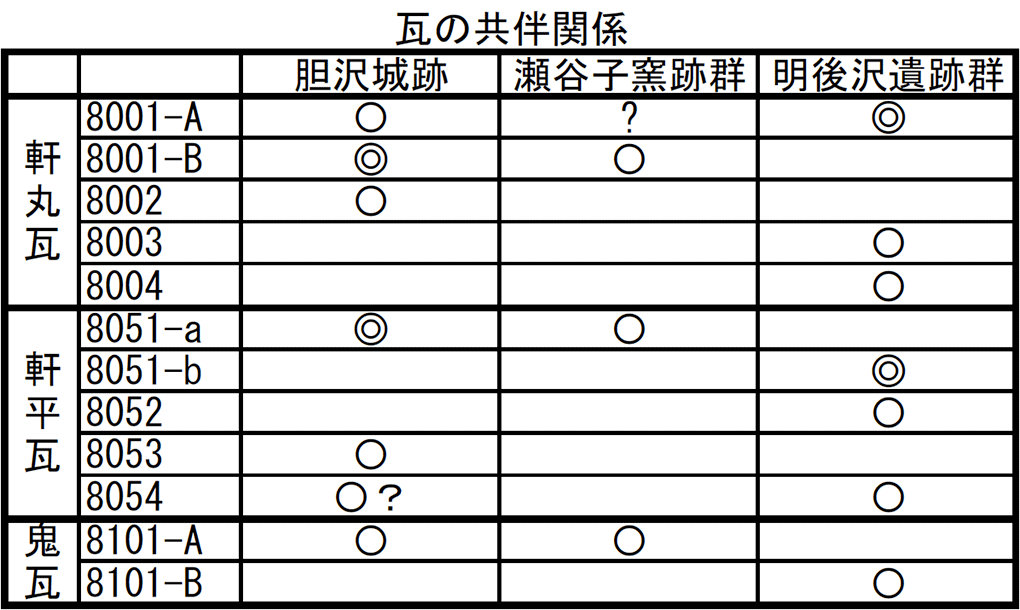#15 文月 瀬谷子窯跡群出土瓦について(3)
2025年7月1日
表1は各遺跡の瓦の共伴関係を示したものです(各タイプの図は前回のコラムを参照してください)。
胆沢城の軒丸瓦は八葉重弁蓮華文軒丸瓦8001-Aと同8001-Bが出土していますが、中心となるのは8001-Bタイプです。この他に七葉素弁蓮華文軒丸瓦8002タイプも出土しています。軒平瓦は連珠文軒平瓦8051-aタイプと無紋軒平瓦8053タイプ、鬼瓦は8101-Aタイプが出土しています。これらのうち、軒丸瓦8001-B・軒平瓦8051-a・鬼瓦8101-Aが組むことが確認されており、外郭南門などの建物の屋根を葺いた瓦の組み合わせと考えられています。また、軒丸瓦8002や軒平瓦8053は当初葺いた瓦が壊れた際の補修瓦と考えられます。
瀬谷子窯跡群からは胆沢城の主体となる瓦である軒丸瓦8001-B・軒平瓦8051-a・鬼瓦8101-Aが出土しており、瀬谷子窯跡群で製作された瓦が胆沢城に供給された様子が伺えます。ただし、胆沢城の補修瓦である軒丸瓦8002や軒平瓦8053については、今のところ瀬谷子窯跡群からは出土していないので、瀬谷子窯跡群からは供給されたものか否かは不明です。
次に明後沢遺跡群については、軒丸瓦が八葉重弁蓮華文軒丸瓦8001-Aと八葉素弁蓮華文軒丸瓦(中房無)8003・同(中房有)8004、軒平瓦は連珠文軒平瓦8051-b・同8052、無紋軒平瓦8054、鬼瓦8101-Bが出土しています。主体となる瓦は軒丸瓦8001-A・軒平瓦8051-b・鬼瓦8101-Bで、他の瓦は補修瓦かと思われます。
明後沢遺跡群の瓦は胆沢城跡や瀬谷子窯跡群の瓦と類似しますが、細かく分類すると両者には違いがあることが分かります。また、瓦を作る時の型である笵(はん)の調査結果から胆沢城跡や瀬谷子窯跡群よりも明後沢遺跡群の瓦の方が新しいことが判明しています。更に、明後沢遺跡群単独で出土する瓦もあります。
これらのことから、瀬谷子窯跡群は胆沢城に瓦を供給していますが、明後沢遺跡群には供給していない可能性が大きいと考えられます。
明後沢遺跡群は胆沢城と同じ瓦が出土する遺跡として古くから注目されており、県指定の史跡となっています。しかし、遺跡の性格については古代の寺院説、覚鱉(かくべつ)城を想定した城柵説、そして窯跡説などの学説が唱えられていますが、その実態は不明なままです。瓦の出土状況や粘土採掘坑の存在などからは窯跡説が有力なのですが、今のところ肝心の窯跡が見つかっていません。
瀬谷子窯跡群の瓦にまつわる問題点、特に明後沢遺跡群との関係についてはあと一歩のところまでたどり着いているような気がしますので、今後の調査や研究の進展が望まれるところです。

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)
1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。
1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。
1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。
退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。
2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。
2024年、えさし郷土文化館長就任。